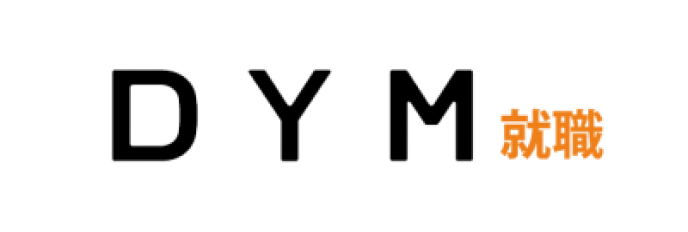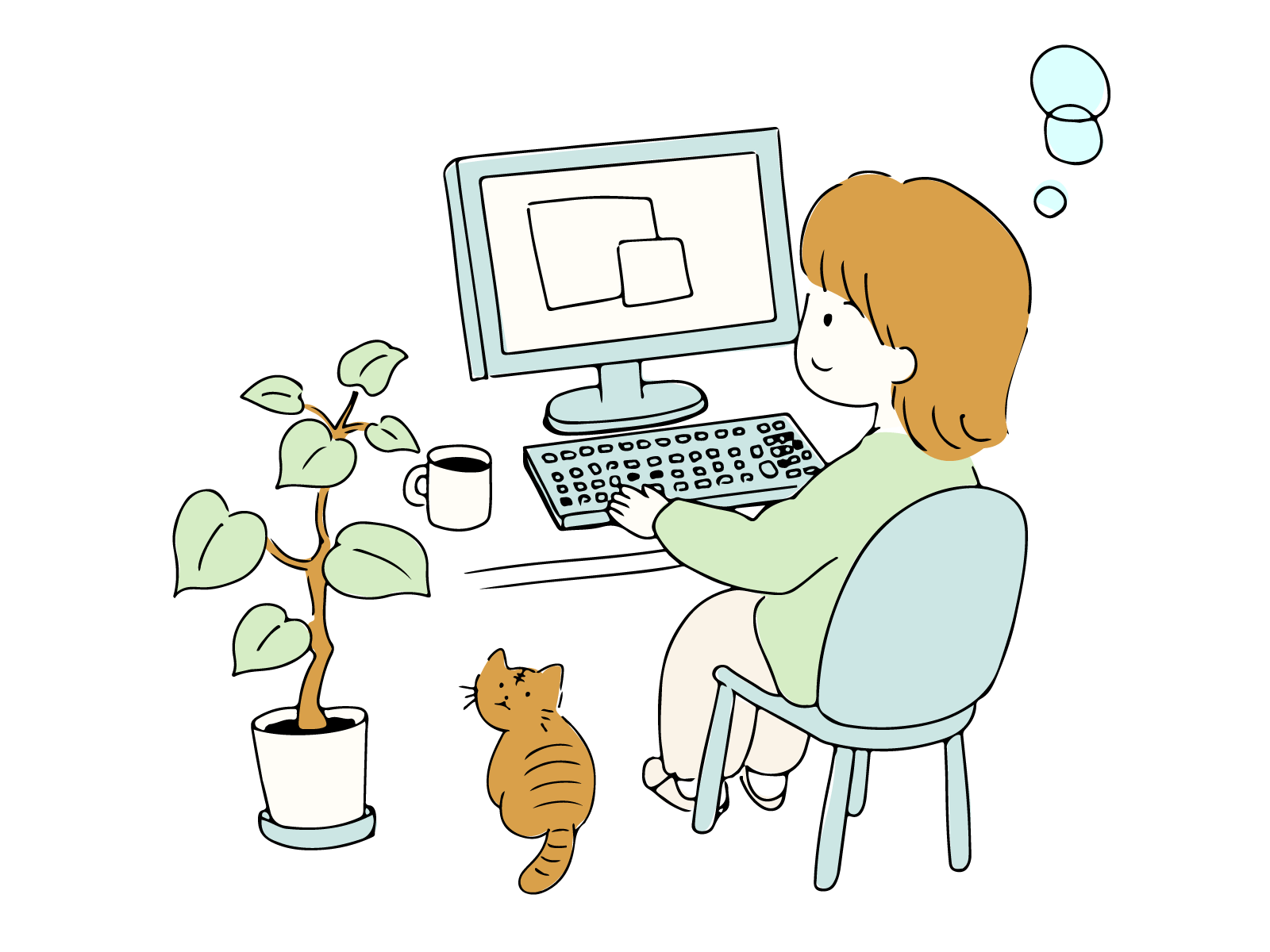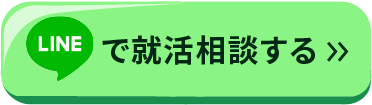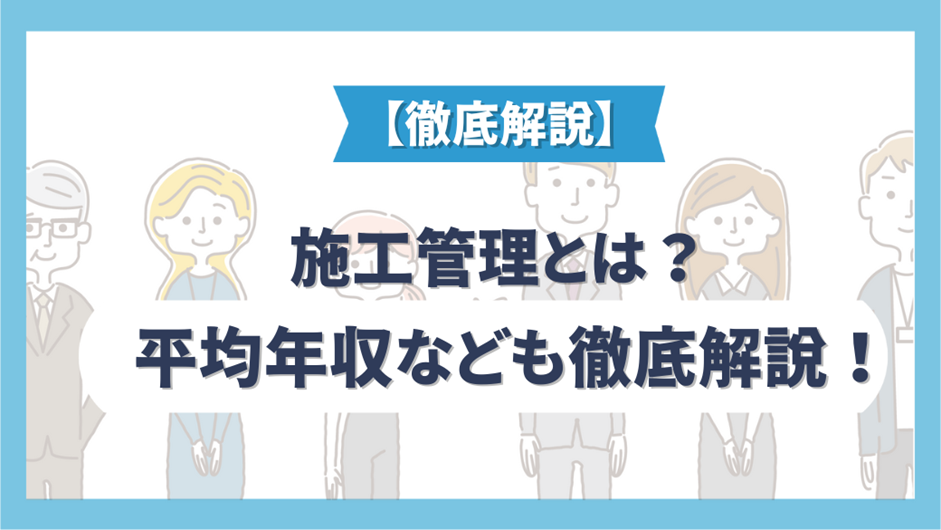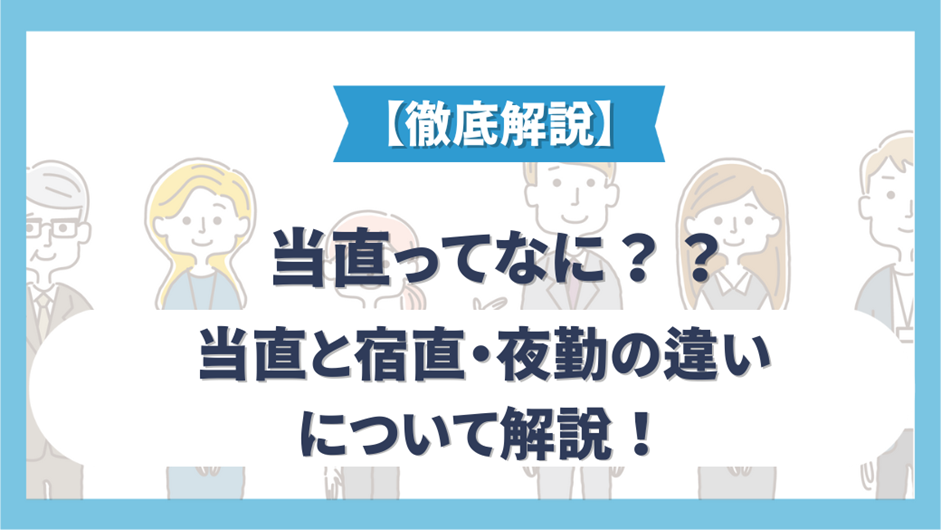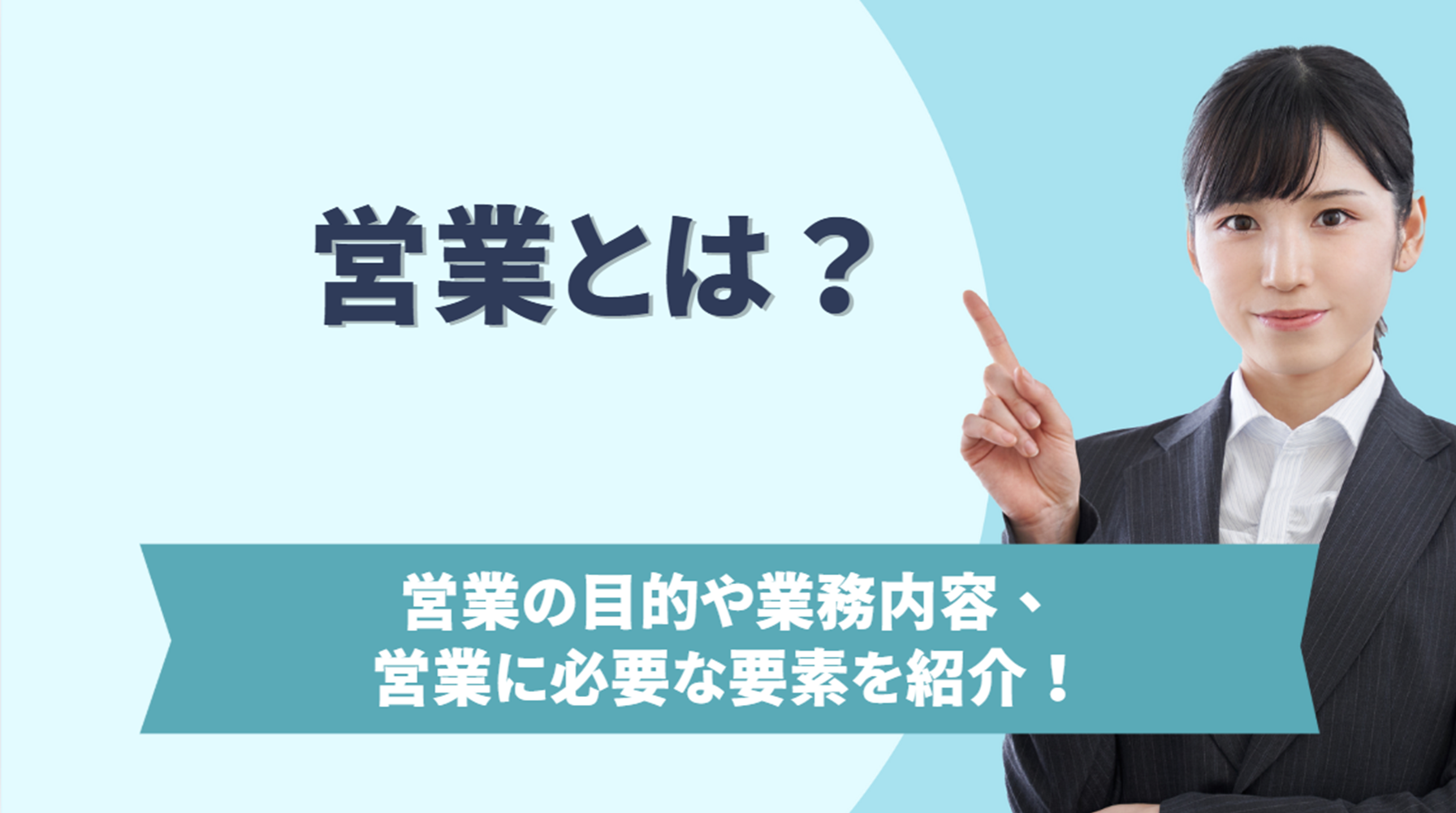未経験からデザイナーへ!独学・転職のリアルと成功戦略

目次
はじめに
未経験からデザイナーになれるのか?
デザイナーの職種紹介
未経験からデザイナーになるステップ
ポートフォリオ制作のコツと注意点
スキル証明に役立つおすすめ資格
デザイナーとして働く方法
よくある質問と回答
まとめ
はじめに
「未経験からデザイナーになれるのだろうか?」「独学で本当に仕事が見つかるの?」
そんな疑問や不安を抱えていませんか?SNSやネット上では「Webデザイナーはやめとけ」「未経験は厳しい」といった声もあり、挑戦をためらってしまう方も少なくありません。
実際、スキルや経験がない状態からのスタートは決して簡単ではなく、仕事が辛い・求人が見つからないと感じることもあるでしょう。
しかし、正しい学び方や準備、そして「デザインが好き」という情熱があれば、未経験からでもデザイナーへの道は開けます。この記事では、未経験からデザイナーを目指すあなたの悩みに寄り添い、独学・転職のリアルや成功のための具体的な戦略を詳しく解説します。
未経験からデザイナーになれるのか?

未経験でもデザイナーを目指すことは十分可能です。多くのデザイナー職は必須資格がなく、未経験者歓迎の求人もあります。
採用される際はポートフォリオ(制作実績集)が重要視されます。ポートフォリオとは、自分のデザイン作品や制作スキルをまとめた資料で、実力を具体的に示すための必須ツールです。
そのため、独学やスクールで学びながら作品を制作し、魅力的なポートフォリオを作ることが大切です。近年はフリーランスとして自由に働く選択肢も増えています。
デザイナーを目指すのに年齢制限はない
Webデザイナーをはじめ、多くのデザイン職は年齢に関係なく挑戦できます。採用では年齢よりもスキルやポートフォリオ、そして学び続ける意欲が重要視されます。
年齢が上がると学習時間の確保や新技術の習得が難しく感じることもありますが、計画的な学習で十分対応可能です。さらに社会人経験や他業種で培ったスキルは、デザイナーとしての強みや個性にもつながります。
柔軟な働き方ができる職種のため、30代・40代から目指して活躍する人もいます。重要なのは年齢ではなく、「なりたい」という熱意と継続する姿勢であり、誰でもデザイナーへの道を開くことができます。
求められる技能
未経験からデザイナーを目指す場合、「特別なセンスが必要」と感じるかもしれませんが、実際には基礎知識やツール操作など、努力と学習で身につけられる技能がほとんどです。
ここでは、未経験者がまず身につけたいスキルを紹介します。未経験からでも努力次第で身につけられるため、コツコツ学んでいくことがデザイナーへの近道となります。
デザインの基礎知識
色彩やレイアウト、フォント、余白などの基本原則を理解することで、論理的に伝わるデザインができるようになります。書籍、オンライン講座などで体系的に学べます。
デザインツールの操作スキル
Photoshop、Illustrator、Figmaなどの基本操作を習得しましょう。簡単な画像加工やバナー作成から始めて、スキルを徐々に広げることが大切です。
模写・実践によるアウトプット力
好きなデザインの模写や自主制作を繰り返し、基礎知識の定着と応用力アップを図ります。作成した作品はポートフォリオとして活用しましょう。
情報収集とトレンド感度
SNSやデザイン系サイトで最新トレンドに触れる習慣を持ち、感性や発想力を磨きます。自分の目標に合った情報を選ぶことも重要です。
コミュニケーション力
クライアントやチームの要望を正確に理解し、わかりやすく伝える能力が求められます。信頼関係を築き、プロジェクトを成功に導くために不可欠です。
デザイナーになるための資格
デザイナーになるために必須の資格はありません。しかし、知識やスキルを客観的に証明できる資格を取得しておくと、未経験からデザイナーを目指す際に学習意欲や基礎力をアピールでき、就職や転職で有利になります。資格はあくまでスキルの裏付けであり、実務ではポートフォリオの重要性が最も高いことも覚えておきましょう。スキル証明に役立つおすすめ資格については、後ほど詳しく紹介します。
デザイナーの職種紹介

デザイナーには多様な職種があり、活躍する分野や仕事内容はさまざまです。ここでは主なデザイナーの種類と特徴を分かりやすく紹介します。どんなデザイナーを目指すか悩んでいる際の参考にしてください。
Webデザイナー
Webデザイナーは、企業や個人のWebサイト、オンラインショップ(ECサイト)、広告用バナーなどのデザインを担当する職種です。
見た目の美しさだけでなく、ユーザーが使いやすいレイアウトや操作性も考慮しながら制作を行います。
また、HTMLやCSSといったコーディングの基礎知識が求められることが多く、デザインデータをWeb上で正しく表示させるための実装作業にも関わる場合があります。未経験から目指す場合は、デザインスキルに加えて、こうしたコーディングの基礎を学ぶことが重要です。
グラフィックデザイナー
グラフィックデザイナーは、ポスターやチラシ、ロゴ、パッケージなどの紙媒体や広告のデザインを担当します。
商品の魅力を視覚的に伝えるために、色彩やレイアウト、フォント選びなどのデザインの基本を駆使して制作します。
デジタルツールの操作スキルも必須で、Adobe PhotoshopやIllustratorなどのソフトを使って仕上げることが一般的です。未経験から目指す場合は、これらの基礎技術とセンスを磨くことが大切です。
UI/UXデザイナー
UI/UXデザイナーは、アプリやWebサービスの使いやすさ(ユーザーインターフェース:UI)と利用者の体験(ユーザーエクスペリエンス:UX)を設計する職種です。
ユーザーが直感的に操作できる画面構成やデザインを考え、満足度を高めることが求められます。
市場調査やユーザーテストをもとに改善を重ねるため、デザインだけでなく分析力やコミュニケーション能力も重要です。未経験から目指す場合は、デザイン知識に加え、ユーザー視点を持つスキルを身につけることが必要です。
CGデザイナー
CGデザイナーは、ゲームや映画、アニメなどで使われる2D・3Dグラフィックや映像制作を担当する職種です。
キャラクターや背景、エフェクトのデザインからアニメーション制作まで幅広く関わります。
専門のソフトウェア(Maya、Blender、After Effectsなど)の操作スキルが求められ、技術力と創造力が重要です。未経験から目指す場合は、ソフトの習得とともに、映像表現の基礎や制作工程の理解を深めることが大切です。
ファッションデザイナー
ファッションデザイナーは、衣服やアクセサリーのデザインを手がける職種です。
デザインだけでなく、流行やトレンドの分析も重要で、市場のニーズに合った魅力的なアイテムを創り出します。
素材選びや色彩感覚も求められ、企画から製品化までの全工程に関わることもあります。未経験から目指す場合は、デザイン技術とともにファッション業界の動向を学ぶことが大切です。
インテリアデザイナー
インテリアデザイナーは、住宅や店舗の内装デザインや家具の設計、空間のトータルコーディネートを担当します。
快適で機能的な空間づくりを目指し、色彩や素材の選定、レイアウトの工夫など幅広い知識が必要です。
CADソフトなどの専門ツールの操作スキルも求められます。未経験から目指す場合は、空間デザインの基礎とツールの習得が重要です。デザイナーとして、住みやすく魅力的な空間を創る役割を担います。
イラストレーター
イラストレーターは、書籍や広告、Webサイト、ゲームなどで使用されるイラスト制作を担当します。キャラクターや背景、アイコンなど多様なイラストを描き、視覚的にメッセージを伝える役割があります。
デジタルツールのスキルはもちろん、絵の技術や表現力が求められます。未経験から目指す場合は、基本的な描画力を磨きつつ、PhotoshopやIllustratorなどのソフト操作も習得することが重要です。
他のデザイナー職
デザイナーには他にも多様な職種があり、プロダクトデザイナーやインダストリアルデザイナー、空間デザイナー、建築デザイナー、映像やモーショングラフィックス専門のデザイナーなど、活躍の場は広範です。各分野で必要な知識やスキル、取得すると役立つ資格も異なるため、未経験からデザイナーを目指す際は、自分の興味や将来像に合わせて学びを深めることが重要です。
未経験からデザイナーになるステップ
未経験からデザイナーを目指すには、段階的にスキルを身につけることが大切です。
まずは基本的なデザイン知識やツールの使い方を学び、実際に作品を作りながら経験を積みましょう。
その後、ポートフォリオを作成し、求人に応募する準備を進めます。継続的な学習と実践を繰り返すことで、未経験からでも着実にプロのデザイナーへと成長できます。
まずは何から始める?最初にやるべきこと
未経験からデザイナーを目指す場合、まずはデザインの基礎知識を身につけることが重要です。色彩やレイアウト、フォントなどの基本原則を理解することで、見た目のバランスや伝わりやすさを意識したデザインができるようになります。
同時に、PhotoshopやIllustratorなどの主要なデザインツールの使い方にも慣れていきましょう。最近ではオンライン教材や動画講座が充実しているため、自宅で自分のペースで学習できます。簡単なバナーやポスター作成など、実際に手を動かしながら作品を作ることで実践力が高まり、学んだ知識を定着させることが可能です。
この段階でしっかり基礎を固めることが、未経験からデザイナーになる第一歩となります。
独学・スクール・職業訓練の違いと選び方
未経験からデザイナーを目指す際の学習方法には、主に3つあります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選ぶことが大切です。ここから詳しく説明します。
独学
独学は、自分のペースで学べて費用を抑えられ、興味のある分野に絞って効率よく学べます。習慣化し継続することで、着実にスキルアップが可能です。自分に合った教材や方法を選び、毎日少しずつ学ぶことが成功のコツです。
まずは「どんなデザインを学びたいか」を明確にし、目標や勉強計画を立てましょう。基礎知識は書籍や参考書、YouTubeなどの動画教材、学習サイトを活用して学びます。
また、優れたデザイン事例を日常的にたくさん見ることも大切です。ギャラリーサイトやSNSで他のデザイナーの作品を研究し、なぜ良いと感じるかを言語化してみましょう。
インプットだけでなく、模写や自主制作などアウトプットも積極的に行いましょう。自分の作品を作ることで、知識が定着し、実践力が身につきます。
オンライン講座・スクール
オンライン講座やスクールは、未経験からでも効率よくデザインを学べる人気の学習方法です。自宅で好きな時間に受講できるため、仕事や家事と両立しやすいのが大きな魅力です。
多くのオンラインスクールでは、PhotoshopやIllustratorなどのデザイン作成アプリの基本操作から、ポートフォリオ制作の実践まで体系的に学べるカリキュラムが用意されています。
現役デザイナーによるマンツーマン指導や、チャットサポート、課題添削、就職・転職サポートなど、サポート体制が充実しているスクールも多いです。短期集中型やサブスク型、女性専用、ママ向けなど、自分のライフスタイルや目的に合わせて選べます。
オンライン講座やスクールは、独学でつまずきやすいポイントも丁寧にフォローしてもらえるため、効率よく実践力を身につけたい方や、就職・転職を目指す方に特におすすめです。
就職しながら学ぶ
企業に就職して研修を受けながら学ぶ方法も有効です。多くの企業では、新人デザイナー向けにデザインの基礎知識やツールの使い方、最新トレンド、実務に直結する課題への取り組みなど、現役デザイナーから直接指導を受けられる研修プログラムを用意しています。
この方法のメリットは、実際の仕事の流れやチームでのコミュニケーションを体験しながら、実践的なスキルを効率よく身につけられる点です。研修を通じてフィードバックをもらい、自分の課題や強みを把握しやすくなります。また、研修後も先輩やメンターのサポートを受けながら成長できる環境が整っています。
就職して研修を受けることで、独学やオンライン講座では得られない現場感覚や実務経験、チームワークの大切さも学べるため、未経験者にとって安心してスキルアップできる選択肢と言えるでしょう。
副業やアシスタントから始める方法も
未経験からデザイナーを目指す場合、まずは副業やアシスタント業務で実務経験を積む方法があります。実際の仕事現場での経験は、スキル向上だけでなく、仕事の流れやクライアント対応を学ぶ貴重な機会です。
クラウドソーシングやアルバイトで簡単な案件から始め、実績を少しずつ増やしていくことで、自信と経験が身につきます。
また、こうした実務経験はポートフォリオの充実にもつながり、就職や案件獲得時に大きな強みとなります。未経験者が早期に現場に触れることで、より実践的なスキルと理解を深められるため、積極的にチャレンジすることをおすすめします。


ポートフォリオ制作のコツと注意点
ポートフォリオはデザイナーとしての実力を証明する重要なツールです。
未経験からの就職や案件獲得には、魅力的で分かりやすいポートフォリオ作りが欠かせません。ここでは、効果的なポートフォリオ制作のコツと注意すべきポイントを紹介します。
ポートフォリオに必要な3つの要素
ポートフォリオには「プロフィール」「スキル」「実績」の3つの要素が必要です。
プロフィール
プロフィール欄では、簡潔な自己紹介とデザイナーを目指す理由をまとめましょう。自分の強みや価値観、これまでの経験を短く分かりやすく伝えることで、採用担当者に印象を残すことができます。
また、志望動機や将来のビジョンも一言添えると、より熱意が伝わります。写真やイラストを使って個性を表現するのも効果的です。全体として、読みやすさと親しみやすさを意識し、第一印象で興味を持ってもらえる内容に仕上げましょう。
スキル
スキル欄には、自分が使えるデザインツールや技術、得意分野を具体的に記載します。例えば、PhotoshopやIllustrator、Figmaなどのソフト名や、Webデザイン、ロゴ制作、イラスト作成などの専門分野を明記しましょう。
資格や受講した講座、独学で学んだ内容もアピールポイントになります。実際の制作工程や工夫した点も簡単に説明すると、スキルの深さや応用力が伝わりやすくなります。
実績
実績欄では、これまでに手がけた作品やプロジェクトを写真や説明付きで掲載します。作品ごとに制作意図や工夫したポイント、使用したツールや担当した役割も具体的に記載しましょう。
可能であれば、成果やクライアントの評価、受賞歴なども添えると説得力が増します。作品のビジュアルだけでなく、その背景やプロセスも伝えることで、デザインに対する考え方や姿勢をアピールできます。
制作物の選び方とよくあるNG例
ポートフォリオに掲載する制作物は、完成度と多様性を重視して選ぶことが重要です。特に、自分の得意分野やスキルを最もよく表現できる作品を厳選しましょう。
未完成やクオリティの低い作品は避け、採用担当者があなたの能力やアウトプットの幅を正しく評価できるようにすることがポイントです。
また、作品ごとに制作意図や工夫した点、担当した役割を明確に説明し、デザインの背景や思考プロセスも伝えることが大切です。
NG例としては、説明が不足している、デザインに統一感がない、画質が悪い、過剰な装飾で見づらい、掲載作品を多くしすぎて重要なものが埋もれてしまう、といった点が挙げられます。採用担当者に伝わりやすく、見やすいレイアウトや説明の工夫を意識しましょう。
採用担当がチェックする3つのポイント
採用担当者がポートフォリオで特に重視するのは、「デザインセンス」「技術力」「問題解決力」の3つです。
デザインセンス
配色やレイアウト、全体のバランス、独自性などからデザインセンスが評価されます。作品ごとに一貫した世界観やテーマが伝わることが大切です。採用担当者は、第一印象で「魅力的か」「個性があるか」を重視してチェックします。
技術力
使用しているデザインツールの習熟度や、仕上がりのクオリティから技術力が判断されます。細部まで丁寧に作り込まれているか、最新の技術やトレンドを取り入れているかも重要な評価ポイントです。
問題解決力
制作物ごとにどんな課題があり、どのように解決したかが明確に説明されているかが見られます。課題設定や工夫した点、改善プロセスなどが論理的に伝わることで、実践的な対応力がアピールできます。
ポートフォリオの作り方
ポートフォリオは、自分のスキルや実績を分かりやすく伝えるための大切なツールです。魅力的な作品と整理された構成で、採用担当者に印象を残すことができます。ここでは、ポートフォリオ作成の主な6つのステップについて順にご紹介します。
1.目的を明確にする
ポートフォリオを作る際に目的を明確にすることは大切です。
たとえば、「Webデザイナーとして就職したい」「ロゴやバナーのデザインを中心にアピールしたい」など、自分が目指す職種や得意分野をはっきりさせることで、どんな作品を載せるべきか、どのような構成にするかが決まります。
目的が明確だと、見る人(採用担当者やクライアント)にも「この人は何ができるのか」「どんな仕事に向いているのか」が伝わりやすくなり、印象に残りやすくなります。結果として、自分に合った仕事やチャンスをつかみやすくなるのです。
2.ポートフォリオの構成・デザインを考える
まず「見やすさ」と「分かりやすさ」を意識しましょう。
各作品にはタイトルや簡単な説明、制作意図や工夫したポイントを添えると、あなたの思考や強みが伝わりやすくなります。
デザイン面では、色やフォントを統一し、全体に一貫性を持たせ、アピールしたい作品は最初に配置して印象づけましょう。最後に、連絡先やSNSなど、応募先がコンタクトを取りやすい情報も忘れずに記載します。
このように、情報を整理し、シンプルで統一感のあるデザインにまとめることで、ポートフォリオ全体の完成度が高まり、あなたの魅力がより伝わりやすくなります。
3.作品を制作する
実務経験がなくても、自分で作品を制作することはポートフォリオ作成の第一歩です。書籍やオンライン講座の課題を参考に、バナーやチラシ、Webサイトなどを作ってみましょう。
慣れてきたら、架空のクライアントや自分の趣味をテーマにしたデザインにも挑戦すると、表現の幅が広がります。
また、気になるWebサイトや広告を模写し、なぜそのデザインが優れているのかを分析することで、実践力が身につきます。知人や地元のお店のチラシやSNS画像をボランティアで制作するのも実績になります。
大切なのは、「自分がどんなデザインが得意か」「どんな工夫をしたか」を作品ごとに説明できるようにしておくことです。数をこなすことでスキルアップと自信が得られ、未経験でも魅力的なポートフォリオを作ることができます。
4.掲載作品を厳選する
ポートフォリオに掲載する作品は、数を多くしすぎず、特に自信のあるものや自分の強みが伝わるものを厳選することが大切です。
一般的には10~20点程度が適切とされており、作品が多すぎると一つひとつの印象が薄れてしまいます。
また、応募先企業の求めるスキルやテイストに合った作品を選び、バリエーションや完成度の高さが伝わるラインナップにしましょう。インパクトのある作品や自分らしさが表現できているものは、ポートフォリオの前半に配置すると効果的です。
厳選した作品には、それぞれ制作意図や工夫した点などの説明も添え、見る人があなたのスキルや考え方を理解しやすいように工夫しましょう。
5.フィードバックをもらい、改善する
ポートフォリオを作成したら、必ず第三者からフィードバックをもらいましょう。自分では気づきにくい改善点や、見る人の視点での印象を知ることができ、クオリティ向上につながります。
身近な友人やデザイナー、講師、SNSのコミュニティなどに見てもらい、率直な意見やアドバイスを受け取ることが大切です。特に、デザインの見やすさや伝わりやすさ、作品の選び方、説明文の分かりやすさなどについて意見をもらうと良いでしょう。
フィードバックを受けたら、素直に受け止めて改善に活かしましょう。何度も見直し・修正を繰り返すことで、より完成度の高いポートフォリオに仕上がります。こうしたプロセス自体が、デザイナーとしての成長にもつながります。
オンラインで公開する
ポートフォリオは、自分の作品やスキルを多くの人に見てもらうために、オンラインで公開することが効果的です。Webサイトや専用のポートフォリオサービスを利用すれば、世界中どこからでもアクセス可能になり、就職活動や案件獲得のチャンスが広がります。
公開方法としては、自分でポートフォリオサイトを作成し、レンタルサーバーにアップロードする方法や、オンラインプラットフォームを活用する方法があります。
また、SNS(Instagram、X、Pinterest)やクリエイター向けプラットフォーム(ココナラ、SKIMA)で作品を公開する方法もあり、拡散力やグローバルな発信力を活かせます。
公開時には、連絡先やSNSアカウント、問い合わせフォームを分かりやすく掲載し、閲覧者がすぐにコンタクトを取れるようにすることが重要です。このようにオンラインでポートフォリオを公開することで、自分の作品を効果的にアピールし、仕事やキャリアの幅を広げることができます。
スキル証明に役立つおすすめ資格
デザイナーとしてのスキルを証明するために、資格取得は効果的な手段の一つです。
特に未経験からのスタートでは、資格が学習意欲や基礎知識の裏付けとして評価されます。ここでは、デザイナーにおすすめの資格とその活用方法について解説します。
アドビ認定プロフェッショナルとは?
アドビ認定プロフェッショナルは、PhotoshopやIllustrator、Premiere Proなどアドビ製品の操作スキルや知識を公式に証明する国際的な資格です。
試験は各アプリケーションごとに独立しており、全国の試験会場でCBT(コンピュータ試験)形式で実施されます。
合格するとデジタル認定証が発行され、就職や転職、フリーランスの案件獲得時にスキル証明として活用できます。デザインやクリエイティブ業界での信頼性が高く、キャリアアップやスキルアップの指標としても有効です。
Photoshop/Illustrator能力認定試験の違い
Photoshop能力認定試験は写真編集や画像加工のスキルを、Illustrator能力認定試験はロゴやイラストなどベクター画像作成のスキルを評価します。
それぞれの試験は基本操作から応用まで幅広い内容が問われ、実務で役立つ知識と技術の証明になります。
自分が目指すデザイン分野や業務内容に合わせて選択するのがおすすめです。両方取得すれば、より幅広いデザイン案件に対応できるスキルをアピールできます。
DTPエキスパート・色彩検定
DTPエキスパートは、印刷物制作に必要な知識や技術を持つことを示す資格で、主にグラフィックデザイナーやDTPオペレーターに重宝されます。
制作工程や印刷、色管理など実務に即した内容が特徴です。色彩検定は、色の理論や配色技術を体系的に学べる資格で、デザインの質向上やブランディング、クライアントへの提案力強化に役立ちます。どちらも紙媒体や広告制作など幅広い現場で評価される資格です。
資格よりも大切な実務経験とポートフォリオ
資格はスキルの証明として一定の効果がありますが、クリエイティブ業界では実務経験やポートフォリオの方がはるかに重視されます。
実際の仕事で成果を出し、それを具体的な作品としてまとめたポートフォリオは、採用担当者やクライアントがあなたの技術や強みを判断する重要な材料です。
未経験の場合でも、資格取得を学習のモチベーションにしつつ、自主制作やボランティアなどで積極的に作品を増やし、ポートフォリオを充実させることが大切です。
資格はあくまで補助的な役割と捉え、実践を通じて自分の強みや個性をアピールできるポートフォリオを作ることが、採用や案件獲得のカギとなります。
デザイナーとして働く方法
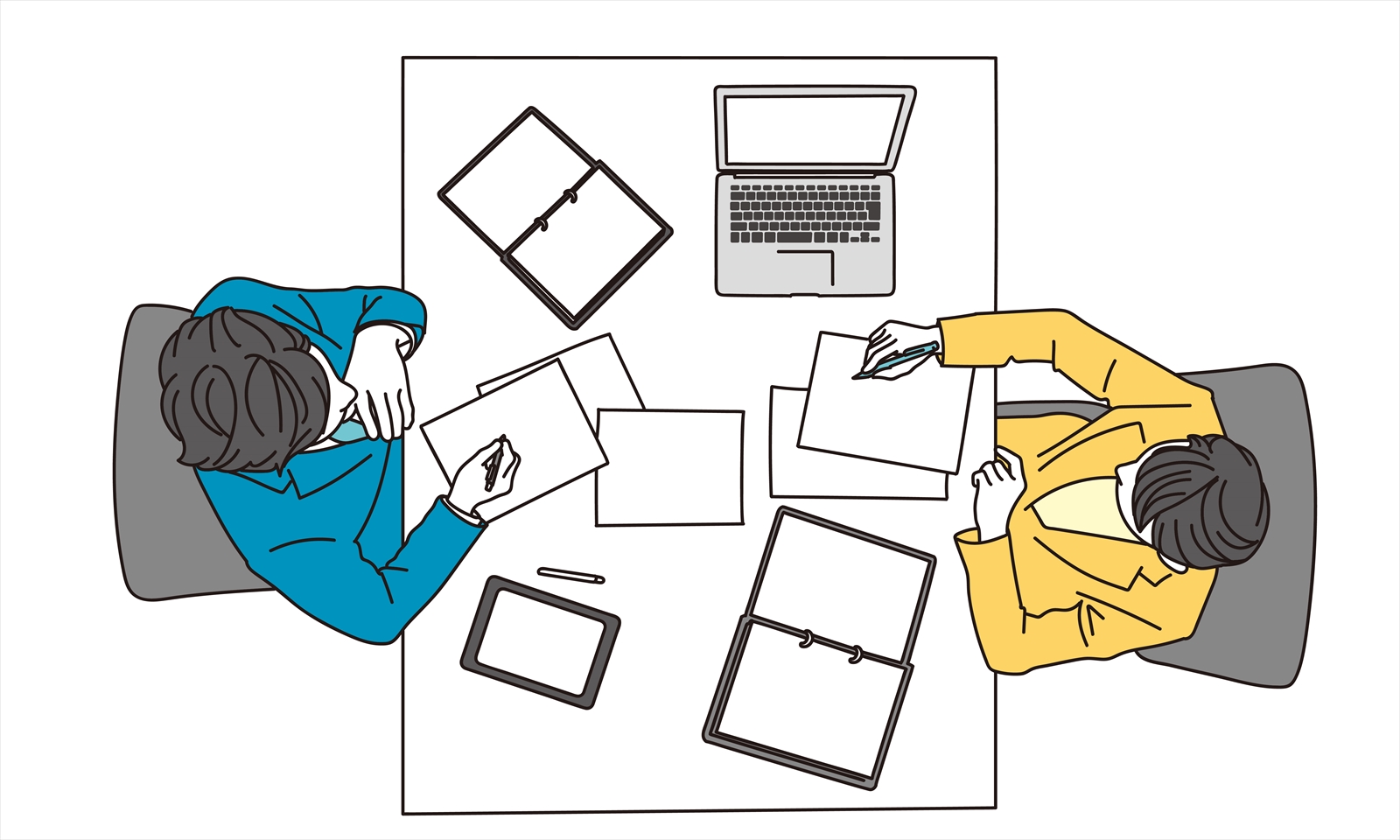
未経験からデザイナーとして働くには、正社員や契約社員、アシスタントとして就職する方法、フリーランスとして独立する方法、副業やアルバイトから始める方法などがあります。自分のライフスタイルや目標に合わせて、最適な働き方を選びましょう。ここではそれぞれの特徴とポイントを紹介します。
就職(正社員・契約社員・アシスタント)
未経験からデザイナーとして働く最も一般的な方法は、企業への就職です。特にアシスタントデザイナーやジュニアデザイナー、インハウスデザイナーなど未経験歓迎のポジションを狙うのがおすすめです。
こうした職種では実務経験を積みながらスキルを身につけられ、キャリアの基盤を築けます。
メリット
- ・基礎から実務まで学べる
企業の研修やOJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じて、現場で必要なスキルや知識を体系的に身につけることができます。 - ・安定した収入と福利厚生
正社員や契約社員として働くことで、安定した給与や社会保険、各種手当などの福利厚生を受けられます。 - ・チームでの経験と成長
先輩や同僚からフィードバックをもらいながら、チームで協力して仕事を進める経験が積めます。
デメリット
- ・配属や業務内容を選びにくい場合がある
会社の方針やプロジェクトによっては、自分の希望とは異なる業務を担当することもあります。 - ・即戦力を求められるケースもある
未経験者歓迎でも、基本的なデザインツールの操作やポートフォリオの提出を求められる場合が多いです。 - ・会社のルールや働き方に合わせる必要がある
勤務時間や働く場所など、自由度はフリーランスに比べて低くなります。
フリーランスとして活動する
未経験からフリーランスのデザイナーになる場合は、自分で仕事を見つけてクライアントと直接やり取りしながら進めます。自由に働ける反面、安定した収入や実績を作るには工夫が必要です。
仕事の取り方には以下の方法があります。
- クラウドソーシングサイトを利用し、初心者向けの案件に応募する。
- X(旧Twitter)やInstagramで作品を発信し、フォロワーやクライアントとつながる。
- 知人や友人から紹介を受け、小さな案件から実績を積む。
- フリーランス向けエージェントやスキルシェアサービス(ココナラなど)を活用して案件を見つける。
これらを組み合わせて仕事を広げていくことが大切です。
メリット
- ・自由な働き方
勤務時間や働く場所を自分で決められるため、生活リズムや家族との時間を大切にしながら、無理なく仕事を続けることができます。 - ・案件やクライアントを選べる
自分の興味や得意分野に合った案件を選び、多様な業界やジャンルに挑戦できるのが魅力です。やりがいのある仕事に集中できます。 - ・収入アップの可能性
実力や実績次第で高単価の案件を受注でき、会社員時代よりも収入が大幅に増えるチャンスがあります。 - ・人間関係のストレスが少ない
組織に縛られず、関わる相手を選べるため、職場の人間関係に悩まされることが少なく、ストレスを感じにくいです。 - ・スキルと経験の幅が広がる
さまざまな案件に携わることで、デザイナーとしてのスキルや知識が自然と広がり、成長を実感しやすい環境です。
デメリット
- ・収入の不安定さ
案件獲得が自己責任となるため、仕事がない時期は収入がゼロになるリスクがあります。また、クライアントの都合で急に仕事がなくなることもあります。 - ・営業・事務作業の負担
仕事の受注や交渉、請求書の発行、確定申告など、デザイン以外の業務もすべて自分で行う必要があります。 - ・自己管理能力が必須
時間や健康、スケジュールの管理をすべて自分で行う必要があり、自己管理ができないと生活が不規則になったり、納期遅れのリスクも高まります。 - ・社会的保障が少ない
会社員と違い、社会保険や有給休暇、傷病手当などの保障がなく、病気やケガで働けなくなった場合のリスクが大きいです。 - ・スキルアップの継続が必要
技術やトレンドの変化が早いため、常に学び続けなければ競争力を維持できません。
副業・アルバイトから始める
未経験からデザイナーを目指す場合、副業やアルバイトからスタートする方法も有効です。特にWebデザインやグラフィックデザインの案件は多く、未経験歓迎や副業・WワークOKの求人も増えています。
副業やアルバイトなら、実務経験を積みながら本業と両立できるため、スキルアップと収入の両立が可能です。また、実際の案件を通じてポートフォリオの充実も図れ、将来的な正社員就職やフリーランス転向の土台作りにも役立ちます。無理なく経験を積みたい方におすすめの働き方です。
メリット
- ・未経験歓迎・研修ありの求人が多い
アルバイトや副業では、研修やOJTが充実している企業も多く、基礎から実務まで段階的に学ぶことができます。 - ・柔軟な働き方が可能
在宅やリモートワーク、週2~3日からOK、1日数時間だけの勤務など、ライフスタイルに合わせて働ける案件が豊富です。 - ・小さな案件から経験を積める
クラウドソーシングやスキルシェアサービス(ココナラ、ランサーズ、クラウドワークスなど)を活用すれば、初心者向けの案件や短期間の仕事からチャレンジできます。 - ・本業と両立しやすい
安定した収入を維持しながら、デザインスキルを実践で磨けるため、リスクを抑えてキャリアを広げられます。
デメリット
- ・案件によっては即戦力を求められることもある
未経験可の求人が多い一方で、実務経験や一定のスキルが必要な場合もあるため、応募前に条件をよく確認しましょう。 - ・収入は安定しにくい
副業やアルバイトは時給や単発案件が中心のため、フルタイム就職やフリーランスと比べて収入が不安定になりやすいです。 - ・自己管理が必要
本業や学業と両立する場合、時間管理や体調管理に注意が必要です。
よくある質問と回答
未経験からデザイナーを目指す方が抱きやすい疑問に答えます。年齢や適性、職種の選び方、資格の必要性など、転職や学習の参考にしてください。
未経験でも何歳までなら目指せる?
デザイナーは年齢制限がほとんどなく、何歳からでもチャレンジ可能です。重要なのは「なりたい」という意欲と継続して学ぶ姿勢です。30代、40代から転職して成功する例も多く、社会人経験が活きるケースもあります。計画的にスキルを磨けば年齢に関係なく活躍できます。
どんな人がWebデザイナーに向いている?
Webデザイナーに向いているのは、細部に気を配りながら論理的にデザインできる人、トレンドや新しい技術に興味を持ち続けられる人です。また、クライアントやチームとコミュニケーションを取りながら仕事を進められる協調性も重要です。好奇心旺盛で柔軟な思考があるとより適性があります。
グラフィックとWebデザイン、どちらを選ぶべき?
どちらも魅力的な分野ですが、働き方や求められるスキルに違いがあります。グラフィックデザインは紙媒体や広告物が中心で、印刷物の知識も必要です。Webデザインはデジタル媒体に特化し、コーディングの基礎知識も求められます。興味やキャリア目標、働き方の希望を考慮して選ぶと良いでしょう。
資格なしでも就職できる?
資格は必須ではありません。実務経験やポートフォリオの質が評価の大部分を占めるため、資格がなくても就職は十分可能です。ただし、資格取得は学習の指標となり、採用担当者にスキルの裏付けを示す手段として有効です。未経験者は資格取得と並行して実践経験を積むことが望ましいです。


まとめ
デザイナーを目指す道は、未経験からでも必ず開けています。今は学びの手段も、仕事のチャンスも、あなたの行動次第でいくらでも広がる時代です。最初は不安や迷いがあって当然ですが、一歩踏み出すことで、あなたの世界は大きく変わります。
ポートフォリオを作り、自分の作品を発信することで、あなたの「好き」や「得意」が誰かの目に留まり、思いがけないチャンスにつながることも珍しくありません。就職、フリーランス、副業、どの道にも可能性があり、あなたらしい働き方を選ぶことができます。
大切なのは、あきらめずに挑戦し続けること。小さな成功や成長を積み重ねることで、必ず自信と実力がついてきます。あなたの「なりたい」を信じて、ぜひデザイナーへの一歩を踏み出してください。未来のクリエイティブな世界で、あなたが輝くことを心から応援しています!

監修者熊谷 直紀
横浜国立大学理工学部卒。株式会社DYMに新卒一期生として2011年に入社し、WEBプロモーションなどのデジタルマーケティング領域で業務に従事し、その後新規事業立ち上げを経験。
2015年よりDYMの人事部へ異動し人事領域を統括、毎年多くの就活生や求職者との面接・面談を実施。
内定チャンネルなどの採用関連メディアへの出演や記事監修を通して人事・人材関連の情報を発信中。

監修者
熊谷 直紀
横浜国立大学理工学部卒。株式会社DYMに新卒一期生として2011年に入社し、WEBプロモーションなどのデジタルマーケティング領域で業務に従事し、その後新規事業立ち上げを経験。
2015年よりDYMの人事部へ異動し人事領域を統括、毎年多くの就活生や求職者との面接・面談を実施。
内定チャンネルなどの採用関連メディアへの出演や記事監修を通して人事・人材関連の情報を発信中。